前回のつづきから
前回の記事では大雑把に額縁作りの工程を書きました。
今回からは、実際に順を追って説明していきたいと思います。
加工そのものは、それぞれの持っている道具・工具や環境が異なるので、全ての方法には言及しません。
実際に作ってみようと考えている方は、手持ちの道具などを考慮して、工夫してみてください。
工夫をしても、どうしても叶わないのであれば、必要な道具を購入してください。
道具や技術を「借りる」ということもあってもいいかもしれません。
これまで、解説してきた、基本的な道具・工具は将来的にも使えます。
無駄にはならないので、今後も楽しみたいと思うのであれば、計画的に揃えるのも悪くは無いと思います。
さて、前回の宿題として、自分の作る額縁は決まったでしょうか?
もし決まったのであれば、その寸法を自分なりに決めて、簡単でいいので図面を書いてみましょう。
前回、「爺の作った色紙額」として書いた、あの程度で充分です。
図面が描けたなら、必要な材料を調達してください。
それでは、前回の工程に沿って、少しずつ進めていきましょう。
工程を進める
木取り
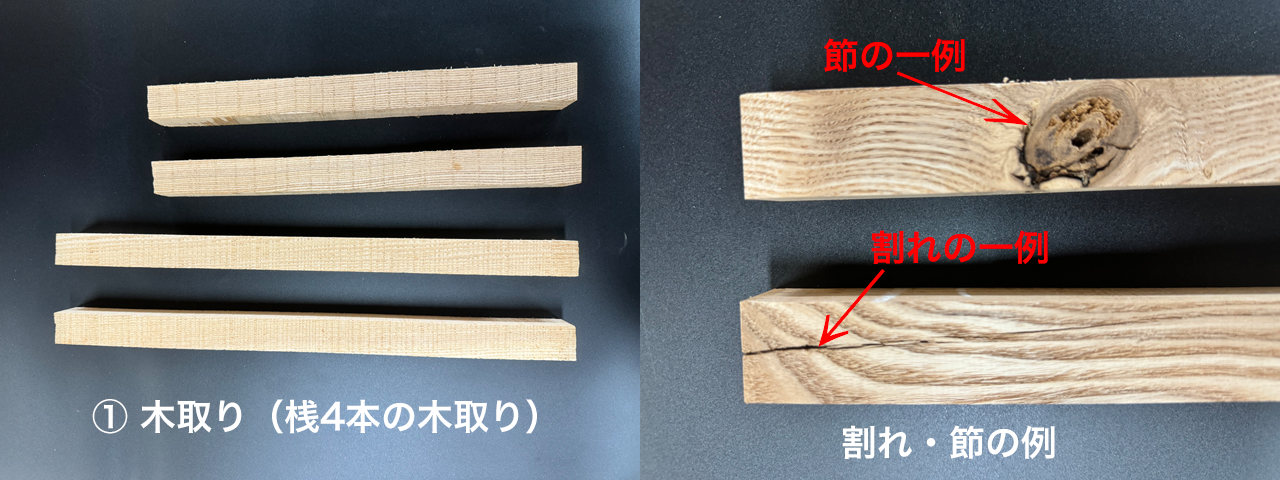
額縁の桟を木取る時には、できるだけ目の通った柾目が良いと言いました。
桟で組み立てることから、それぞれの桟が、後に歪んだりすることを避けたいと言うのがその理由でした。
とは言え、材料には制約もあり、なかなか思うようにならないこともあるでしょう。
上図は、今回の記事のため、爺が木取りをしたものと、節や割れの一例です。
節や割れが絶対にいけないと言っているのではありません。
ものによっては、何とも言えない良い趣になることもあります。
「適材適所」でお願いします。
寸法仕上げ
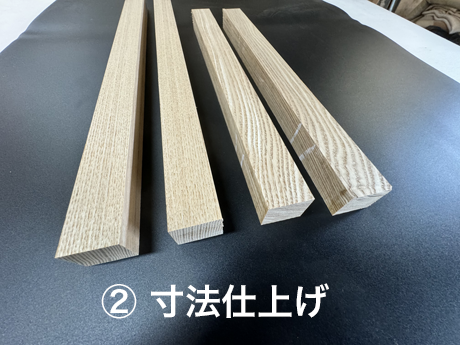
今回の額縁は27×30×321(351)の桟が2本と27×30×292(322)の桟が2本でした。
長さはそれぞれ30㎜程度の余裕をみて( )内寸法で仕上げました。
手道具(鉋や鋸)での作業をする方は、寸法だけではなく、それぞれの面がちゃんと直角(90度)になっているか、それぞれの面が平面になっているかも確認してください。
手間暇はかかりますが「最初が肝心」と言いますので、慌てずに一つ一つ確実に作業していきましょう。(締切はありません(笑))
溝切り

ここまで出来ましたら、いよいよ ガラス・絵・裏板などが納まる溝切りをします。
手道具だけでということだったら、「け引」で墨線を入れ「鉋」や「鑿」で時間をかけて加工する方法もあります。
できれば、「ルーター」か「トリマー」を使う方が美しく仕上がるだけでは無く、効率もとても良いです。
比較的安価で小型の「昇降盤」(丸鋸を逆さにして固定された定盤付きの木工機械です)もヤフオクなどでみかけます。
予算に合い、程度の良いものなら、入手するのも良いかも知れません。
今回のような材の端に溝切りする時には、1番だと思います。
面取り
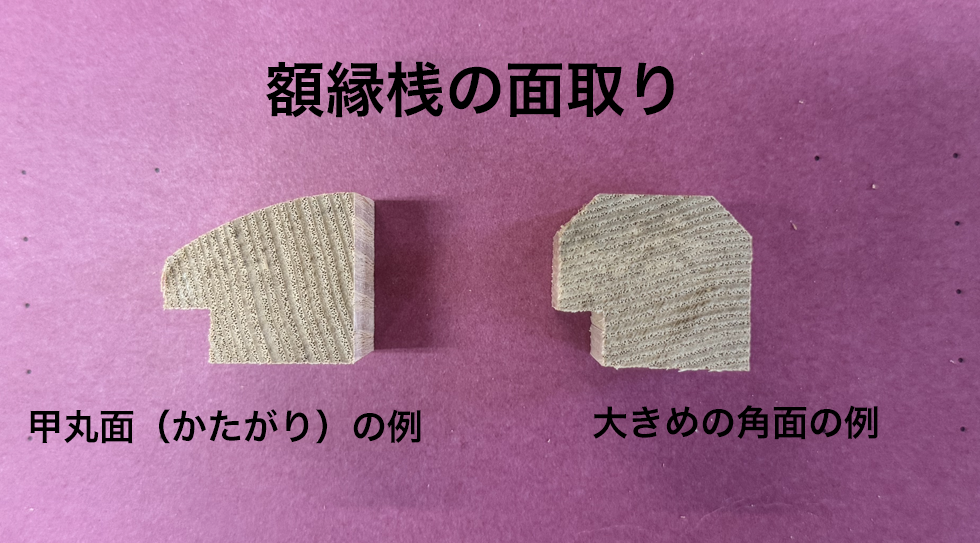
上図は今回解説のために作ってみた額縁の「面取り」例です。
左側は「甲丸(片流れ)」で、右側は大きめの「角面」をトリマーでとったものです。
少し技術のある方は前者に挑戦してみるのもいいですし、そうで無い方は後者でも それなりの額縁ができると思います。
例では内外共同じ大きさの角面になっていますが、大小をつけると、また違った表情になります。
額の表情は この面取りや桟の幅・高さなどで大きく変わります。
それも勉強です。
いきなり作り始めるのでは無く、デザインも楽しんでください。
Let’s try!
追記:額縁作りの途中ですが、しばらく仕事が忙しくなります。
次回は8月中旬になるかもしれません。
ここまでの過程を楽しんでください。
次回まで ごきげんよう!
【関連記事サイト】
「額縁を作ってみよう!(1)」
「額縁を作ってみよう!(2)」
「額縁を作ってみよう!(3)」
「額縁を作ってみよう!(4)」

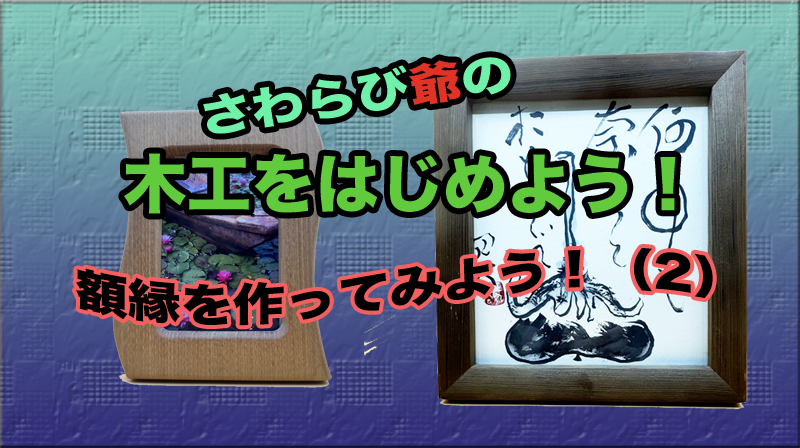
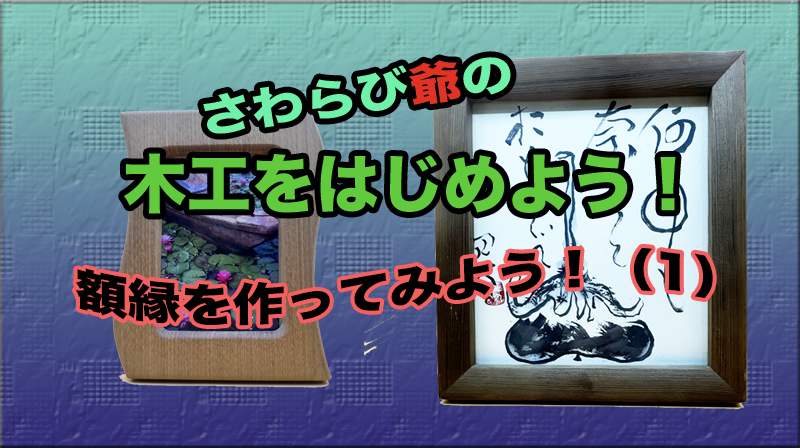
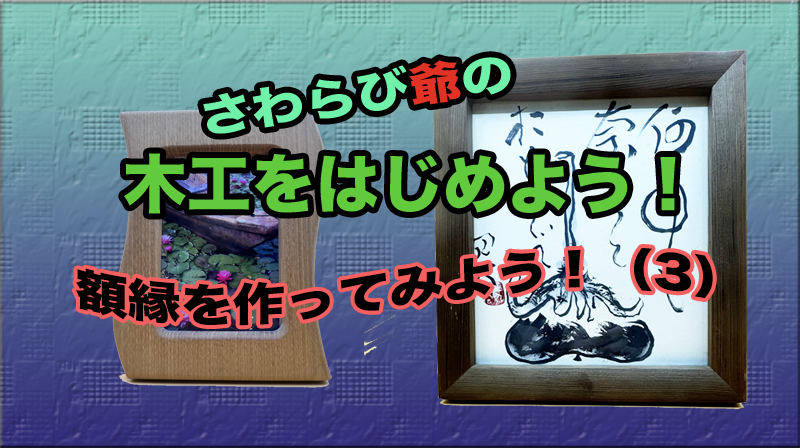
コメント