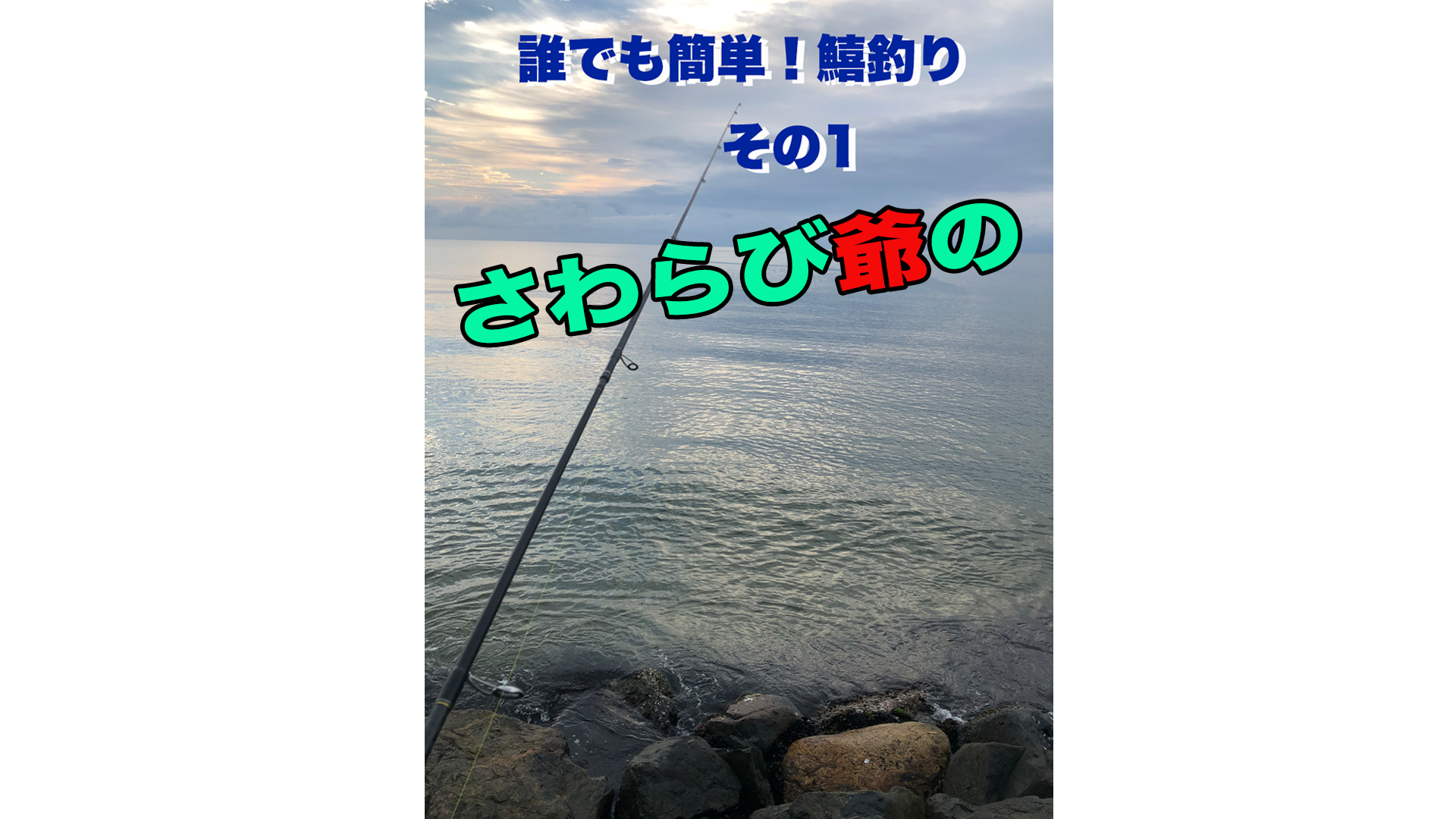鎚(つち)って?
釘うち、組み立て、鑿うち、鉋調整など、強く打ち込む時に用いる打撃用の道具です。
誰でも一度は釘を打った経験があると思います。
「あぁ金槌のことね。」と理解していただけたかと思います。
鎚(つち)と一言で言っても世の中には実に多くの種類があります。
その中でも、木工では主に玄能(げんのう)という鎚を使いますが、大型の掛矢・木槌・プラスティックハンマー、ゴムハンマーなども使う機会があるかも知れません。
爺はほとんどの場合、玄能の大・中・小で事足りています。
ごく稀に・木槌・ゴムハンマーなどを使うことがありますが、撮影しようと作業場を探しましたが、行方不明で撮影には間に合いませんでした。(失笑)
鎚(つち)の種類について
爺の工房にある鎚を揃えてみました。
(上図左側から)
(1) 大型のハンマー(上図一番左)
大型家具の組み立てなどに※「あて木」をして使います。
楔(くさび)を打ち込むときにも重宝します。
※「あて木」部材に傷がつかないように保護する目的で使う木材のこと。
打ち込み時、1点にチカラが加わらない意味もある。
(2) 玄能(げんのう 上図左から2番目・下図も参照願います)
木工をする方の多くがこの鎚(つち)を頻繁に使用すると思います。
釘打ちから、組み立て、鑿(ノミ)の打ち込み、鉋(カンナ)刃の調整等々ほとんど玄能で事足 ります。
大きさ(重さ)については各種揃えた方が使い勝手が良いと思います。
凸面と平面があり、釘打ちの際、打ち込み始めは平面を使い、打ち込み終わりでは凸面で仕上げると部材にキズがつきにくいです。
穴埋め(ダボ埋め)などでさらに深く釘打ちしたい時にはコチラを参考にしてください。
(3) 大工用(釘打ち専用 上図左から3番目)
現在では大工さんは電動やエアー工具の「釘打ち機」を使われることが多いと思います。
この釘打ち専用金槌は、元々西洋から伝来したものだと聞いています。
片面に釘打ち面があり、反対側に釘抜き面があるという、効率的な構造になっています。
(4) 唐紙金槌・いす屋金槌(上図左から4番目・5番目)
元々は襖の「引き手金具」を固定するために釘を打つ時に使う金鎚であったり、椅子張り職人が使ったりと、特殊な専用の金槌と言えます。
小ぶりで軽いので、ホビー用に持っていてもいいかと思います。
このほかにも槌類としては、打面が木製の木槌・打面がゴム製のゴムハンマーや同じくプラスティック製のプラスティックハンマーなど、様々なものがあります。
どんな道具でもそうですが、とりあえずは多用するものをまず求める。
特殊な道具は何か代替できないか工夫をする。
どうしても代替できずに必要に迫られたら、初めて購入を考える。
その様に考えていけば良いのではないかと爺は思います。
と言うわけで、まず木工で必要な鎚類は「玄能(げんのう)」だと言えます。
これは経験上ですが、大・中・小と必要だと思います。
2.(2)で説明したように、用途が多いので元は充分に取れますので、いくつか揃えておかれるといいと思います。
下図は爺が実際に使っている玄能です。
さして高級品でもありませんが何十年も役立ってくれています。

Let’s try!