木ネジについて
用途
木工をやっていて、木材や金具を固定する時などには、
・ 接着剤を使う
・ 仕口(オス・メスの組み木)を使う
・木ネジや釘を使う
・ その他
などありますが、今回は木ネジについて考察してみます。
木工で使う木ネジとしては「コーススレッド」が代表的なものとして挙げられます。
コーススレッドは一般的な木ネジと異なり、ネジ山が粗く深い事と、焼き入れがしてあり、固いことが特徴です。
特に制約のない場合は、このコーススレッドを使うのが良いと思います。
特徴
釘と比較すると木ネジの特徴は、大きくは二つあります。
① 一つめは抜けにくいこと。
一般的に木ネジの保釘力(ほていりき)は、釘の2倍以上あるとされています。
これは、木材の種類・木ネジの直径・食い込み長 等々によって変わるもので、一概には言えないものですが、爺の実感では、2倍どころでは無く、もっと強いものと思っています。
※保釘力(ほていりき):木材から抜けにくいチカラ。引き抜き抵抗。
② 二つめの特徴としては、不要ならばドライバーで、いつでも取り外せることです。
この事は不必要なら抜いてしまえるだけでは無く、種類の異なる木ネジを打ち直すことも可能であるという事になります。
これらの理由から、爺の工房では「釘」よりも圧倒的に「木ネジ」を多用しています。
一方で、大工さんは「釘打ち機」や「タッカー」などの使用が多いことから、木ネジよりも広い意味での「釘」の方が多用されているものと思われます。
木ネジの種類について
素材・色
木ネジの素材は、鉄(鋼)・真鍮・銅・黄銅・ステンレスなどが一般的です。
一般的には鉄(鋼)製のもので良いのでしょうが、例えば水回りなど錆やすい環境で使うのであれば、ステンレス製の木ネジを使うべきでしょう。
また、個人的な話ですが、爺は制約が無い扉の場合は厚手の真鍮製蝶番を多く使います。
そんな時は、当然ながら真鍮製の木ネジを使います。
金具などが黒色であれば、黒色の木ネジを使うであるとか、そんな気配りは当然あるべきでしょうね。
DIYショップを見て回ると、本当に様々な木ネジが並んでいます。
木ネジばかりではありませんが、時々DIYショップを覗いて見ると、新たなインスピレーションに恵まれるかもしれません。(おすすめします。)
すりわり(マイナス)と十字(プラス)

図-1
木ネジの頭部は、締め付けたり緩めたりするために溝穴が付けてあります。
一般的な木ネジでは「すりわり」と言われる「マイナスドライバー」に対応するものと、「十字」形のプラスドライバーに対応するものがあります。(図-1参照)
両者共それぞれ、大きさがあり、頭部の切り込みにピッタリのドライバーを使う習慣をつけましょう。
丸皿ネジ・皿ネジ・丸ネジ

図-2
木工で使う木ネジについては、頭部の形状で、大きく三つに分類出来ます。(図-2参照)
図-2の左側から「丸皿ネジ」「皿ネジ」「丸ネジ」となります。
木工で最も多用するコーススレッドは形状とすれば皿ネジになります。
丸皿ネジや丸ネジは頭部に丸みがあるので、蝶番の取り付けには不向きです。
逆に金具取り付けなど、場合によっては丸皿ネジや丸ネジの丸みのある頭部が適している場合もあります。
適材適所ですね。
全ネジ・半ネジ

図-3
図-3をご覧ください。
左側が全ネジ、右側が半ネジです。
その名の通り、全面的にネジ切りしてあるか、途中までネジ切りしてあるかの違いです。
木材どうしをネジ留めする場合、お互いの板を引きつけ合うチカラは半ネジの方が強いと言われています。
実際にそのように感じます。
何故ならネジ山を切っていない部分が板をくっつける方向に押し付けるからです。
一方で、固定するチカラは全ネジの方が強いと言われています。
当然のことながら、板と木ネジの接するすべての部分に溝が当たっているからです。
この二つのニュアンスの違いはしっかりと理解していただきたいと思います。
木ネジを使う時の注意点
予備穴(下穴)を確実に

図-4
木ネジを使う時には、必ず予備穴(下穴)をあける習慣にしましょう。
一般的にはコーススレッド(特にスリムビス)は予備穴(下穴)無しでも大丈夫と言われています。
しかし、それは絶対ではありません。
図-4をご覧ください。
これは予備穴(下穴)無しで、ドライバードリルでコーススレッドを打ち込んだ例です。
問題は二つあると思います。
一つは、いくらスリムタイプのコーススレッドでも、その長さや材木によっては、割れが生じること。
二つ目は、材木の固さや木目によっては、真っ直ぐに木ネジが入っていかない場合があることです。
ですから、余程のことが無い限り予備穴(下穴)は必須だと考えましょう。

図-5
参考までに、皿ネジ系の予備穴(下穴)を掘る時に爺が使っているビットを紹介しておきます。(図-5参照)
爺の場合は予備穴の深さは木ネジの半分から2/3程度。
予備穴の直径は木ネジ径の60%〜70%を基本としています。
予備穴(下穴)の具体的なあけ方は、自分に合った方法を模索してみてください。
ドライバードリルの使用時の注意点
今ではドライバードリルがDIYを趣味としていない人にまで普及しているように思われます。
そこで蛇足かも知れませんが、注意点を挙げておきます。
それはドライバードリルのパワーとスピードに関するものです。
特に慣れないうちはビットの選択を間違えたり、しっかりとセットできていないのにいきなり高速回転させてしまうなどして、木ネジの頭部の溝をナメてしまうことです。(頭部をネジ切ったりしてしまう失敗も考えられます。)
締めることも緩めることも出来なくなるので、充分に気をつけましょう。(緩める裏ワザはありますが..)
また、木ネジだけでは無く、肝心の材料を潰してしまう事にも注意が必要です。
材料の端に近いところで木ネジを使う時には、特に注意が必要です。
Let’s try!
本日の1本 008 最高の人生の見つけ方
【本日の1本 008 最高の人生の見つけ方】
今回の「木ネジ」から連想される映画を考えた時に、実は2本のタイトルが思い浮かびました。
1本は「最強のふたり」で、もう1本がこの「最高の人生の見つけ方」でした。
偶然にも、どちらも、まったく異なった境遇の二人が、強い友情で「惹きつけ合う」という物語です。
木ネジの仕事を考えた時、二つのものが「引きつけ合う」と、まるで駄洒落のような発想ではあります。
今回は「最高の人生の見つけ方」を紹介しますが、両者とも素晴らしい映画ですので、まだ観ていない方には、お薦めいたします。
さて、ストーリーですが、モーガン・フリーマン演じる自動車整備工のカーター・チェンバースとジャック・ニコルソン演じる大富豪エドワード・コールが互いに癌を患い、病院で同室となる出会いから、「死ぬ前にやりたい事リスト」(これが原題になっています。)に従い世界を股に駆け回るという物語です。
その間に笑いあり涙あり感動の展開です。
特にラストシーンでは、ユーモアと重い事実とが交錯するといった、秀作です。
泣いたり笑ったりしたい時には効能のある映画です。
日 付: 20250714 記事no. 055
原 題 :The Bucket List
邦 題 :最高の人生の見つけ方
配 給: ワーナー ブラザーズ
公 開 :アメリカ:2007年12月25日 日本:2008年5月10日
主な俳優:ジャック ニコルソン モーガン フリーマン

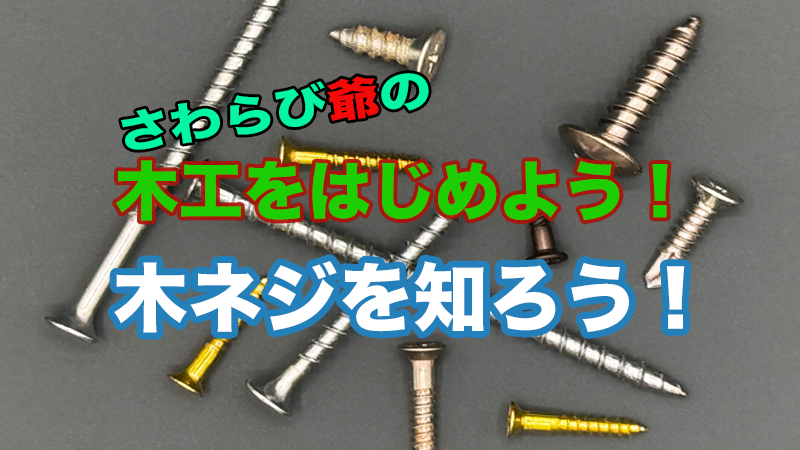

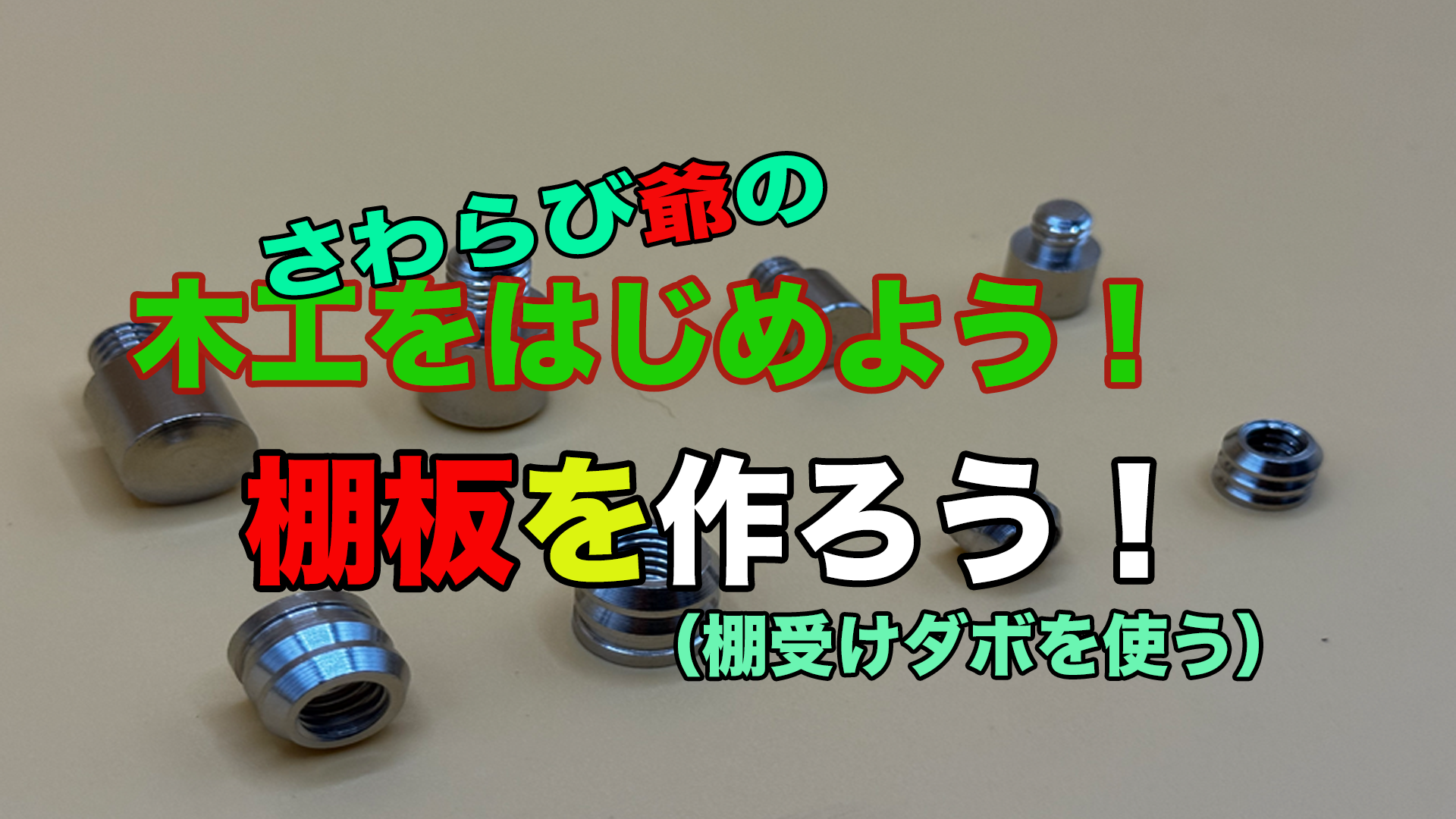
コメント