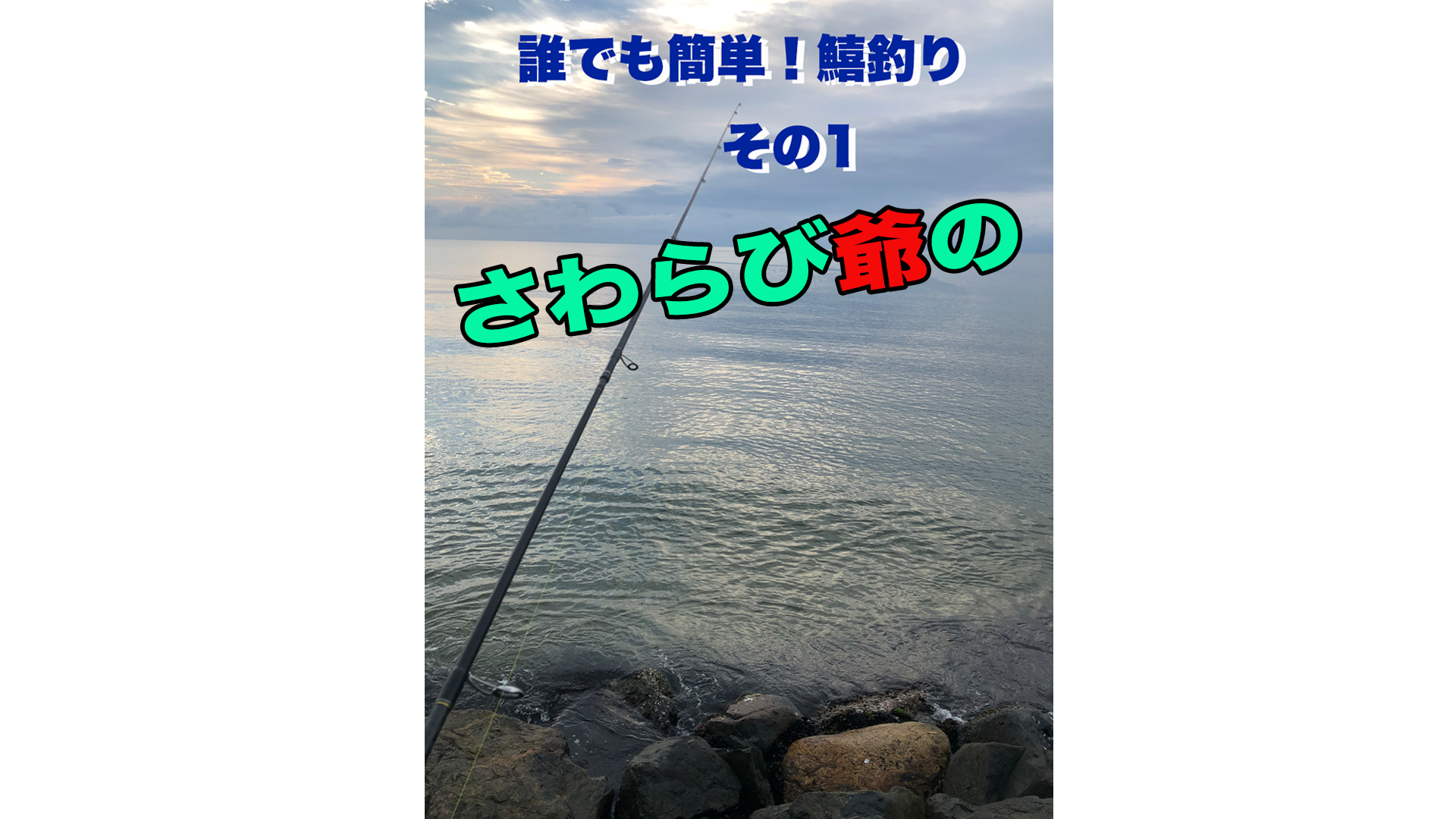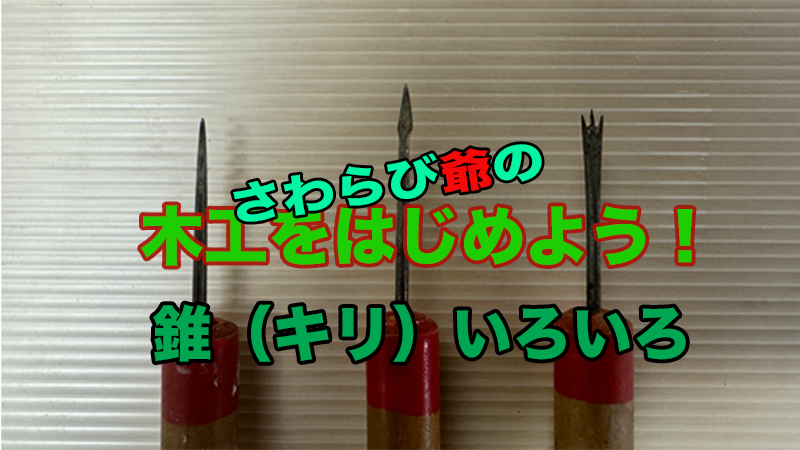け引きとは…
「け引き」は「罫引き」とも書きます。 櫛型の定規板に平行に線が引けるように刃の付いた竿を直角に取りけたものです。
ネジか楔(くさび)で任意の位置に刃を固定できるようになっています。
け引きの種類
(1) 筋け引
罫書き用途には一番多く使われるもので、ホゾ穴の罫書きには重宝します。
爺の工房では、け引きはほぼこの筋け引だけを使っています。
(2) 二本竿け引き
一枚の定規板の左右にひとつずつ二本の竿を平行につけたもの。
ひとつのけ引きで二種類の罫書き線が引ける。
(3) かまけ引き
竿の中に2枚の刃を通してあるもの。
ホゾ穴の罫書きが一度にできる。
(4) 長竿け引き
幅の広い板に使う。
長い竿が特徴。
(5) ほぞけ引き
建具屋さんや家具屋さんなどで角ノミの寸法に合わせて二つの刃を仕込んであるもの。
ホゾ穴の罫書きには効率が良いのですが、爺は大昔に建具屋さんで現物を一度見たことがある程度です。
(6) 割り付け引き(割け引き)
薄板などを一定幅で桟状に割り落とすけ引き。
本体も刃も頑丈に作ってあり、下部に引きやすいように溝がつけてあります。
「け引き」の使い方(筋け引き)

「け引き」で罫書きたい寸法に定規を使いセットします。
大抵の場合はネジで固定する時にどうしても僅かな誤差が出ます。
この誤差は「け引き」固有のもので、自分の「け引き」の癖のようなものですので、使い込んで覚えてください。
この誤差はコンマ何ミリというものでは無く、使い込むうちに感覚で分かるようになります。
この感覚こそが、「け引き」を使うコツでありポイントとなります。
ネジで固定した後に正確にセットしてあるか、定規で必ず確認しましょう。
あとは下図のように持って罫書き線を引くだけです。

Let’s try!