鉋(かんな)その2
「鉋(かんな)その1」の記事では、代表的な鉋として「平鉋(ひらかんな)」の解説をしました。
鉋は平鉋だけでは無く、多くの種類がありますので、今回は「鉋(かんな)その2」として、いくつかの種類について説明します。

長台かんな
平かんなと同じような形となっていますが、相違点は刃口から台尻までが長い構造になっていることです。
長い材料の鉋がけや、板はぎ(板同士を接着して板幅を広くすること)面の仕上げに使います。
きわかんな
刃先の片方が鉋側面に露出している鉋です。
右勝手・左勝手のものがあり、爺の工房ではホゾの調整などに使います。
台直しかんな
平鉋の刃を垂直に仕込んだ鉋を想像すれば分かりやすいと思います。
鉋台下端(したば)の調整に使います。
また、ごく固い材木..例えば黒檀や紫檀などの材料、アフリカ産のマメ課材料などの平鉋では太刀打ち出来ないような堅木を横ズリして削る時にも使います。
内丸かんな
鉋刃や鉋台を円弧状に仕込んだ鉋で、丸棒状のものや丸面を削る鉋です。
随分以前になりますが、違棚の「筆返し」を加工する時に購入しました。
曲面を整形したり、仕上げたりするのに重宝します。
外丸かんな
内丸鉋同様に、鉋刃や鉋台を円弧状に仕込んだ鉋で、反対に丸溝加工や刳り(くり)加工をする時に使う鉋です。
上述の「内丸かんな」同様に、違棚の「筆返し」を加工する時に購入しました。
曲面を整形したり、仕上げたりするのに重宝します。
溝かんな
鑿(のみ)のような使い方をする鉋です。
仕込んである刃幅の溝をしゃくるのに使います。
今はルーターなどでその作業をしていて、ほとんど使うことはありません。
面取りかんな
材料の面取りに使います。
鉋刃の形によって、角面・ぼうず面・ぎんなん面・きちょう面・さじ面等々の面取りに使います。
爺もいくつか持っていますが、面取りに関してはほとんどの場合トリマーやルーターで取り、サンドペーパー仕上げをすることで用を足しています。
反り台かんな
鉋台下端を船底状態(前後に)反らしてある鉋です。
材を凹んだ形に加工する時に使います。
曲面を整形したり、仕上げたりするのに重宝します。
羽虫かんな
(8)反り台かんなのように前後が反っているだけでは無く、左右にも反っている鉋です。
「刳りもの」(皿や器)の内側を仕上げる時に重宝します。
この工程は嫌いではありません。
無心にこの鉋を使う工程は大好きです。
なんきんかんな
棒状の台中央に鉋刃を付けた鉋です。
両端をそれぞれ両手で持ち使います。
爺の工房では、椅子の曲線部分やロッキングチェアのレッグ部分など、曲線仕上げで、温かみのあるカーブを仕上げる時に使います。
「なんきんかんな」を使う工程は大好きです。
好きすぎて、削り過ぎることがあります。
定規付きかんな
先述の「溝かんな」に定規のついたものです。
一定幅の溝しゃくりだけでは無く、蟻溝用の定規付きかんなもあります。
これについても、爺の工房ではトリマーやルーターで、その用を果たしていて、今はほとんど使っていません。
その他かんな
大工さんをはじめ、建具屋さん・家具屋さんなど木工では、この他にも様々な鉋があると思います。
代表的なものを挙げてみましたが、時代の変遷により、今ではほとんど使われないものもあると感じています。
逆に、今でもしっかりとその役割を果たしている鉋も多くあります。
職人さんがオリジナル手作りで工夫をされている鉋もあると思われます。
実際に、画像の羽虫鉋の小さい方は、私のオリジナルです。
道具や治具を工夫して作ることも木工の楽しみのひとつです。
Let’s try!
【関連記事サイト】


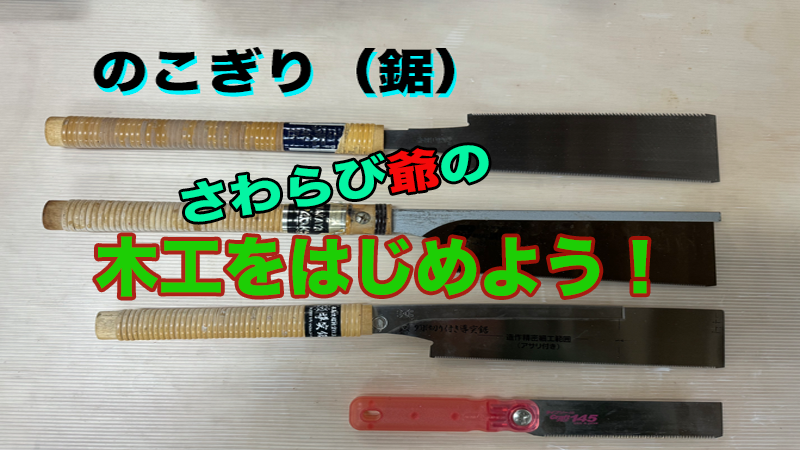
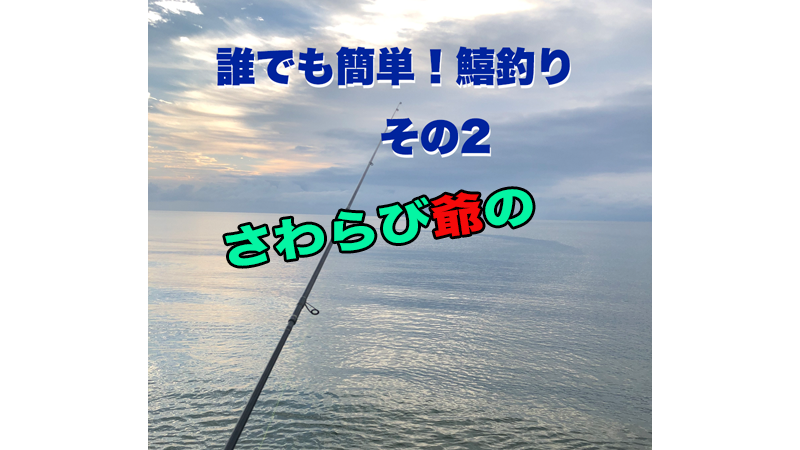
コメント