鉋は 木材を薄く削ることによって仕上げるための道具です。
基本は、今回解説します平面を仕上げる「平鉋」ですが、曲面を仕上げるためのもの、面取りをするためのもの、溝切りをするもの等々あります。
多種多様ではありますが、切削の原理は、ほぼ同じです。

構造
鉋は「鉋台」と「身」から出来ています。
鉋台は樫材などの硬い材料で出来ていて、木表を「下ば」に末口を「台頭」に木取りして作られています。(下図参照)
理由は材木(鉋台)の「反り」と「組織構造」に由来します。
詳しく考えてみると、その確かな理屈に納得できると思います。
「身」というのは鉋の刃のことです。
刃裏には切削のために切れ刃(鋼)が仕込んであります。
刃幅は、身の頭部から刃先へ向かって少し狭く作られています。
身の研ぎや調整の出し入れがし易くなるための工夫だと思います。
このことだけをとっても、日本の木工道具の素晴らしさがうかがえます。
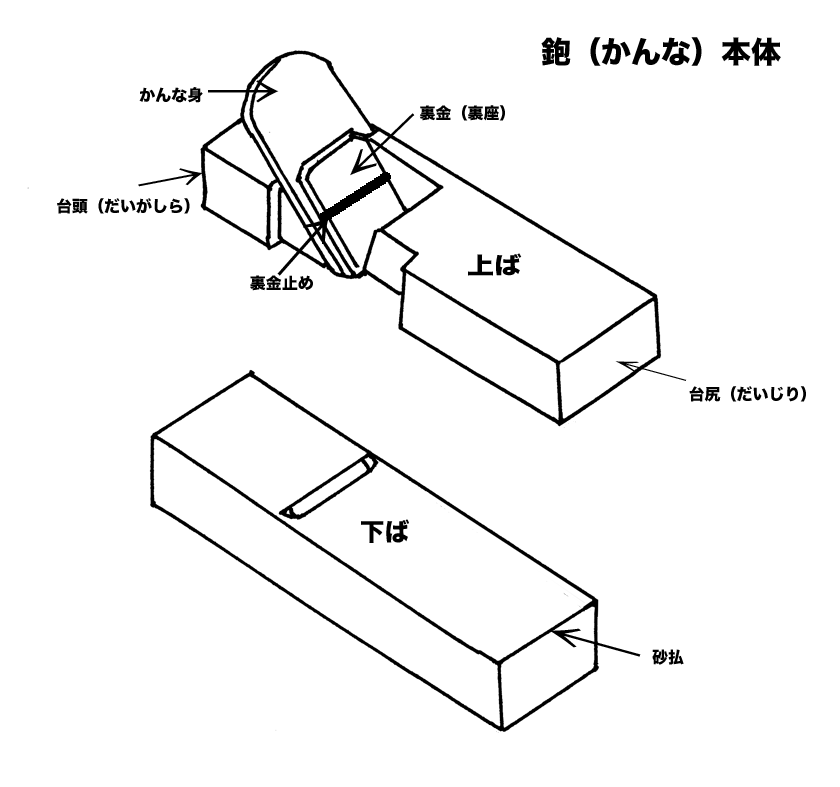
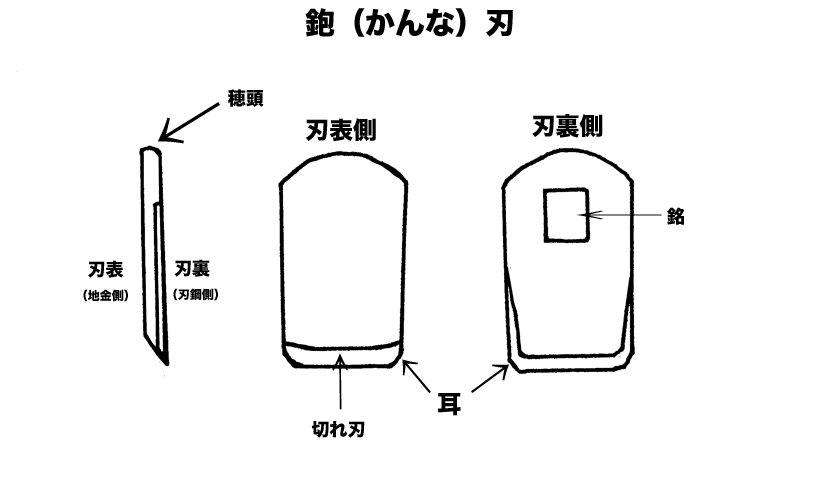
平鉋について(最も一般的な鉋です)
私たちが「鉋」と聞いて1番に思い浮かべるのが、この平鉋でしょう。
切削面の仕上がり状態や仕事量によって、荒削り用の荒鉋(あらしこ)中間の中仕上げ鉋(なかしこ)、仕上げ削りの仕上げ鉋に用途分けします。
鉋身(刃)が一枚だけの「一枚刃鉋」と裏金のある「二枚刃鉋」があります。(下図参照)
一枚刃鉋の特徴は、鉋引きにチカラがいらないことが挙げられます。
その理由は、裏金がないので板当たりの抵抗が少ないことなどです。
しかし、利点と欠点は表裏一体ですので、このことが欠点にも繋がります。
それは、「(※)逆目」(さかめ)が出やすいということです。
もちろん2枚刃の鉋でも逆目は出ますが一枚刃の鉋ほどではありません。
そこで、爺の工房では一枚刃の鉋は板の平面を出す時の「横削り」や額縁の「留め」(45度)などの木口仕上げに使っています。
二枚刃鉋については、今ほどの一枚刃鉋の欠点である切削角度の小ささを補い、微妙な切れ刃の動きをしっかりと抑えることもあり、逆目を起こしにくくしているものです。
とはいえ、「逆目」方向に鉋を引いたり、材料が堅木の杢ものであったりすると、二枚刃鉋でも逆目は出ます。
刃の研磨・台や刃先の調整・鉋の引き方など様々な条件が整い、はじめて鉋がけは上手くいきます。
下図一番右側の鉋は、小さな二枚刃鉋です。
爺は、ホゾのオスをちょっと面取りしたりとか、仕上がりをあまり気にしなくて良い場所の「入り面取り」に使っています。
「(※)逆目」(さかめ)とは…木材を削る時に木目に逆らって削ると「ささくれ」が生じること。また木目に逆らう方向のこと。↔︎「順目」(じゅんめ)

今日のコツ
鉋がけにコツはあるのかな?とここまで書いて、ハタと考えました。
先述のとおり、鉋がけには幾つもの関門があります。
まず、刃物の研磨。
これは鉋に限ったことでは無く、鑿(のみ)であったり、鋸(のこ)であったり
でも同様で、電動工具の「刃」にも同じことが言えます。
次に鉋身(鉋刃)の調整..出入りだけでは無く、鉋台と平行になっている
か?二枚刃鉋であれば裏金と光も漏れないようにピタりと合っている
か? しっかりと整っていること。
3番目には、鉋台がちゃんと出来ているか?
鉋台の「下ば」がねじれていたり、刃口が広がりすぎていてはいけませ
ん。
鉋がけの上達ついては、多くの経験を積むことに尽きます。
これが、本日の一番大切なコツでした。(笑)
最後にもうひとつ。
これはすぐにも出来るコツです。
鉋を置くときには、横向きに置く癖をつけるようにしましょう。
鉋の「下ば」に細かなキズをつけないようにするためでもありますし、使用中の鉋であれば当然「鉋身(鉋刃)」も出ていますよね?
その位の配慮が出来ないようなら、鉋がけの上達は見込めないと思います。
そしてなにより、ちょっとだけプロっぽいじゃありませんか。(苦笑)
それでは、「鉋その2」まで、何度も何度も経験を積んでください。
Let’s try!
【関連記事サイト】

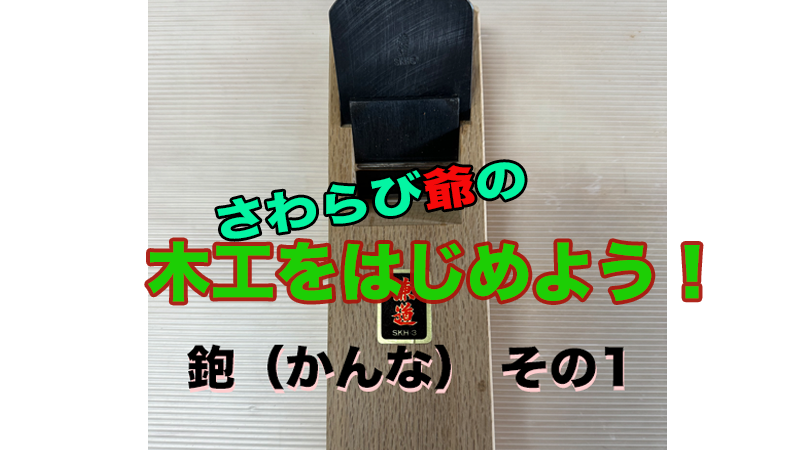

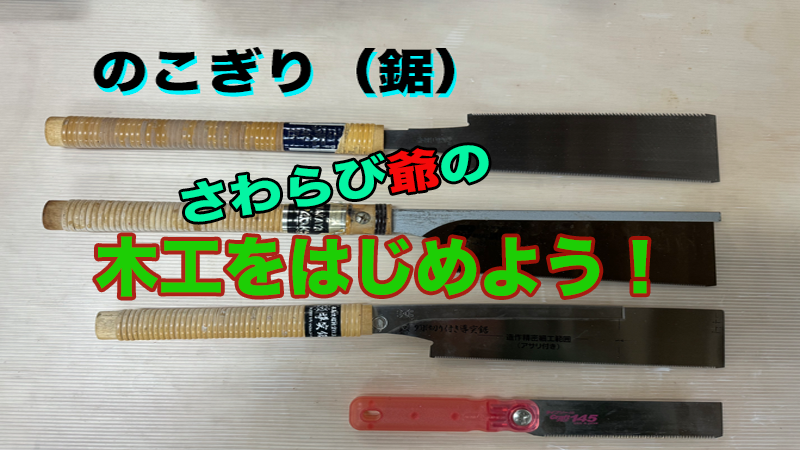
コメント