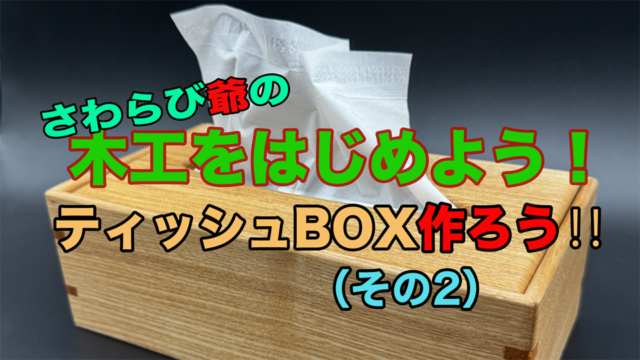 他にも
他にも ティッシュBOXを作ろう!(2)
部品はちゃんと加工が出来たでしょうか? 仮組をして、ちゃんと各部が収まったでしょうか? また、組み立ててからでは仕上げが困難な本体の内側の仕上げは、大丈夫でしょうか? それぞれのチェックが完了したら、いよいよ組み立ての工程になります。
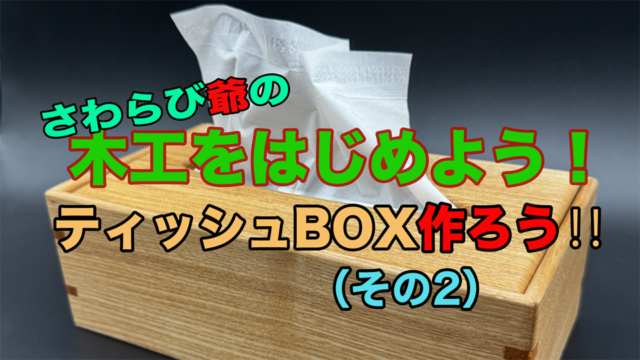 他にも
他にも 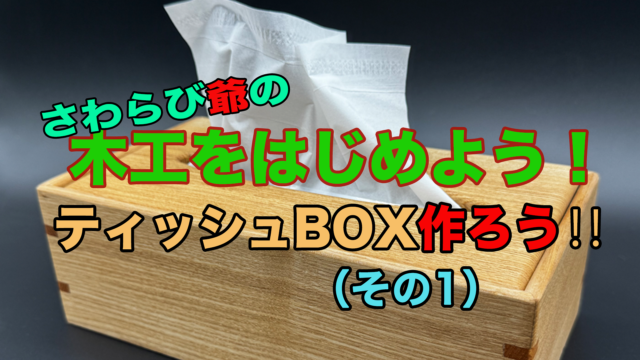 他にも
他にも 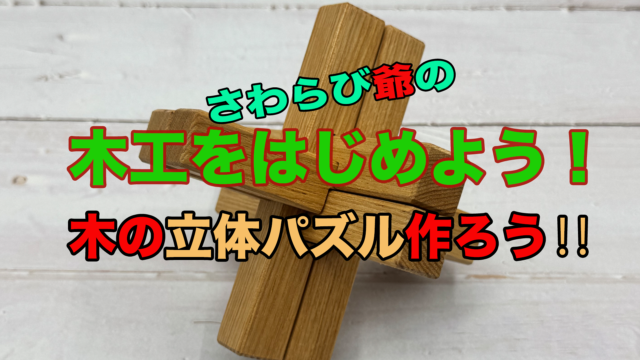 他にも
他にも  加工法
加工法 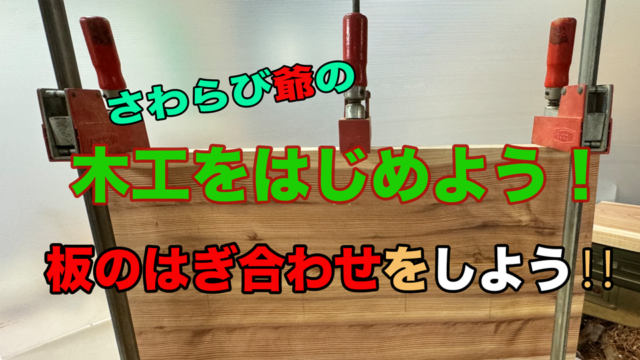 加工法
加工法 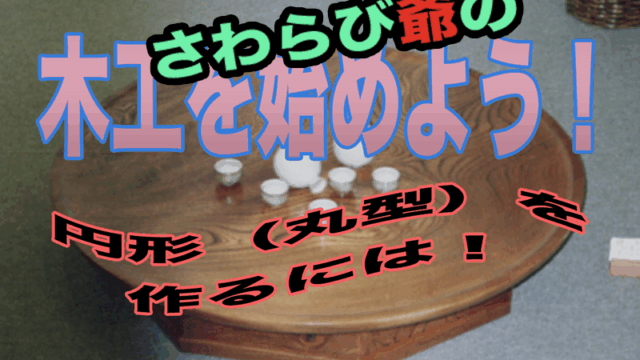 工具・道具・治具
工具・道具・治具 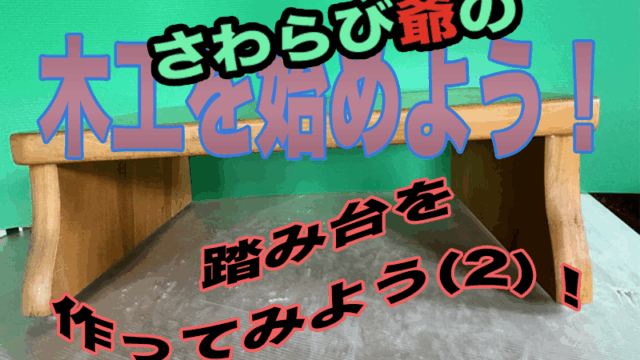 他にも
他にも 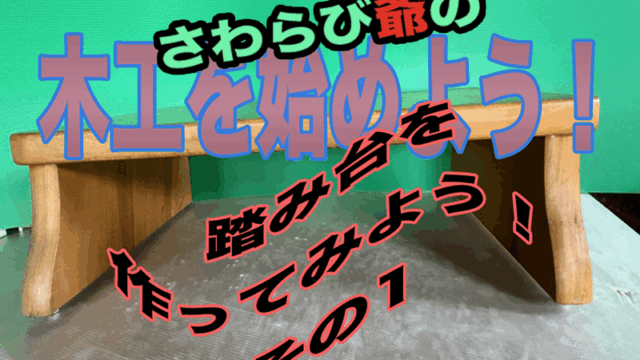 他にも
他にも 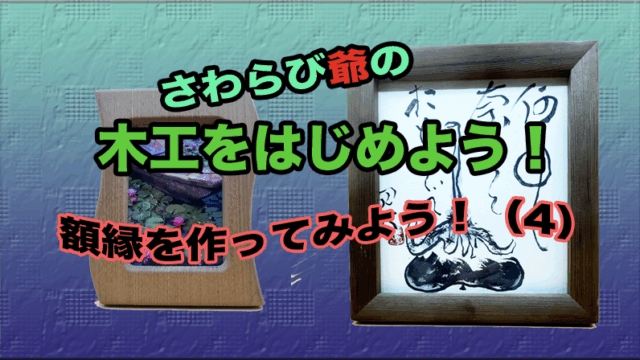 他にも
他にも 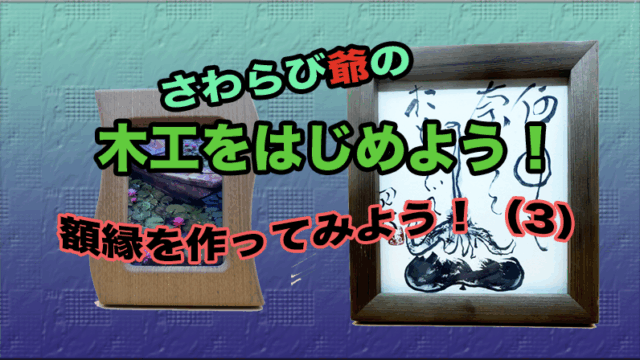 他にも
他にも